
グスタフ・クリムト/10分でわかるアート
2022年6月15日
スフマートでは、「つくる」「つたえる」という2つの視点をもとに、ミュージアムを支えるさまざまな人へのインタビューをお届けしています。
今月は特別編として、美術の専門的な教育を受けることなく、自ら湧き出る創造性をパワーに創作された作品の総称である「アール・ブリュット」について、2人の視点から取り上げます。
まずお話をお聞きしたのは、アーツ千代田 3331でポコラート事業(*)に携わる、嘉納礼奈さんです。
*ポコラート事業:「ポコラート(POCORART)」とは、Place of “Core+Relation ART”「障害の有無に関わらず人びとが出会い、相互に影響し合う場」であり、その「場」を作っていく行為を示す名称のこと。2010年に開館したアーツ千代田 3331と千代田区が共同主催で取り組んでいる事業です。

アーツ千代田 3331 嘉納礼奈さん ※撮影時、マスクを外していただきました。
嘉納さんは芸術人類学を専門とし、『アール・ブリュット アート 日本』(平凡社)の著書ほか、2021年に開催された展覧会、ポコラート世界展「偶然と、必然と、」のメインキュレーターを務め、活躍されています。
前編では、ヨーロッパでの研究活動を通してアール・ブリュットに出会った嘉納さんに、そもそもアール・ブリュットとは何か、日本と他国との違いがあるのか、などについてお伺いしました。
──「アール・ブリュット」という言葉や、そう呼ばれるようになった経緯について教えていただけますか。
アール・ブリュットは、フランス人画家のジャン・デュビュッフェが作り出した言葉です。
デュビュッフェは、専門的な美術教育を受けず独学、あるいは、精神的な病も抱えながら創作活動をする人びとの作品に、第二次世界大戦中から関心を寄せていました。
そして終戦後の1945年ごろから彼らの作品を収集し始め、それらのコレクションを「アール・ブリュット」と名付けたことが始まりです。
デュビュッフェのコレクションは1967年、パリの国立装飾美術館の展覧会で大々的に披露され、非常に話題になり、後世の芸術家たちへも大きな影響を与えました。そのコレクションは現在、スイスのローザンヌ市に寄贈されています。

アール・ブリュットという言葉は現在では世界中に広まり、英訳されて「アウトサイダー・アート」と呼ばれたり、アメリカでは「フォーク・アート」とも呼ばれたりしています。
しかし、現在では国や地域によって、呼び方だけでなく意味合いや言葉が指すものも、デュビュッフェが提唱したものとは異なっています。
それは、国や地域によって歴史や文化的土壌、社会的背景などが異なり、人びととアート、そしてアール・ブリュットをとりまく環境が異なるからです。「アール・ブリュット」という言葉から、その国や地域の政治経済、地域性、社会課題、考え方、価値観などを垣間見ることができます。
──フランスで生まれたアール・ブリュットが日本で知られるようになったのは、いつごろからなのでしょうか。
一般的に、広く知られるようになったのは、2010年にフランス・パリで開催された展覧会『アール・ブリュット・ジャポネ展』が、翌年に日本国内へ巡回したことが大きなきっかけだと思います。この展覧会は、主に福祉業界の関係者たちが企画を進め、障害のある作家が手がけた創作物を中心に構成されました。
この展覧会のタイトルにアール・ブリュットが掲げられたことで、日本国内でこの言葉が知られるようになりました。
国内でのアール・ブリュットの指す意味合いは、デュビュッフェが最初に提唱したものとは違っており、日本では主に、障害のある人たちが制作したアート作品を指す言葉となっています。
言葉は使う人たちによって常に変化していくものです。もしかすると今後、これらのアート作品はアール・ブリュットではなく、全く新しい言葉で呼ばれるかもしれません。
──嘉納さんが「アール・ブリュット」と呼ばれるような作品や作家と出会ったきっかけを教えていただけますか。
私はもともとヨーロッパで美術史の研究や仕事をしていたんです。当時は1940年代後半のアクションペインティングや50年代のフランスのアンフォルメル、1960年代に生まれたヌーヴォー・レアリスムやフルクサスなどパフォーマンス色の強い芸術活動に関心を持っていました。
フランスのジョルジュ・マチウ(1921-2012)や、ニキ・ド・サンファル(1930-2002)、そのパートナーだったジャン・ティンゲリー(1925-1991)などを研究していく中で、ジャン・ティンゲリーの出身地だったスイスへよく取材するようになりました。
──スイスといえば、デュビュッフェがコレクションを寄贈した国ですね。
はい。スイスでは、アール・ブリュットという言葉が生まれる以前から、精神的な病を抱えながら、独学で創作活動をする人びとやその作品が病院などで保存されていました。
私がたまたま他の作家の研究や思想史などの分野を取材していたとき、ジャン・スタロバンスキー(1920-2019)の自宅へ取材に伺うことになりました。
スタロバンスキーは、欧米ではとても有名な思想史家であり、精神医療を学んだ医学博士でもあった人です。精神分析、芸術と文芸を組み合わせた著作を数多く手がけています。
彼の自宅で私は、壁に掛かっていたスイス人の作家、ルイ・ステー(1871-1941)の絵画を目にします。彼の作品は、まるで民族芸術の絵画のように見え、その独自のスタイルにとても驚きました。
スタロバンスキーから、ルイ・ステーの作品が初めはデュビュッフェが「アール・ブリュット」のコレクションに入れていたこと(後にアール・ブリュットからは区別)を教わり、気になって調べ始めたのが、私とアール・ブリュットの出会いでした。
ルイ・ステーは、建築家 ル・コルビジェのいとこにあたり、裕福な家に生まれます。絵画やバイオリンを嗜んでいたものの、離婚や父親との死別から生活が一変し、さらには自身も病気を患い、50代以降に指で絵を描くようになった画家です。
私は彼の作品に出会い、非常に感動しました。
図らずも病気という“断絶”があったから、それまで描いていたアカデミックな絵画の常識を壊し、さらに積み重ねてきた技術も手放して、独自のスタイルで絵を描くようになったのだ、と思ったのです。
──取材先での偶然の出会いがきっかけで、アートとアール・ブリュットと呼ばれる作品の周辺を観ていったのですね。
はい。例えばニキ・ド・サンファルも、自身が精神的な疾患を抱えていたこともあり、アール・ブリュットへの関心が高く、個人的に作品を収集していたことをのちに知りました。
ヨーロッパでは精神医療と芸術は非常に近い場所に存在していて、絶えず現代美術家たちもアール・ブリュットの存在を意識しているのです。
ニキ・ド・サンファルらの次の世代で、インスタレーションを手がけるフランスのアネット・メサジェ(1943-)と、パートナーのクリスチャン・ボルタンスキー(1944-2021)も、1967年のデュビュッフェのアール・ブリュットコレクションの展覧会をパリで観て、生涯自分たちの作品に影響を与えたことを語っています。
──そうなのですね。嘉納さんは2014年ごろに帰国されたとのことですが、帰国当時と2022年の今とで、日本国内にどんな変化や違いを感じていますか。
20年ほどヨーロッパに暮らしていたので、帰国して日本とヨーロッパのアール・ブリュットの意味の違いが鮮明に感じられました。
帰国してから7年以上が経ちましたが、当時より国内の障害のある人びとの芸術表現が多様化していると感じますね。絵画や彫刻制作だけでなく、パフォーマンスをしたり、音楽や言葉を扱ったりと、障害のある人びとの表現手段は多岐にわたっています。彼らの日常の行為を表現と捉えることもしばしば見受けられます。
これはやはり、東京2020オリンピック・パラリンピックに向け、取り組みが急速に広がったためだと考えられます。ここ10年で、障害のある人びとを支えるご家族や支援者の方々の意識も高まり、さまざまな気づきへと発展したのではないでしょうか。
いまや注釈なしで「アール・ブリュット」という言葉が新聞にも載ります。さらに自治体が、障害のある人びとによる作品を展示する機会を定期的に設け、その展示場所も格段に増えていると感じています。
今後どのように、「日本の」アール・ブリュットが展開していくのか、見守っていきたいですね。
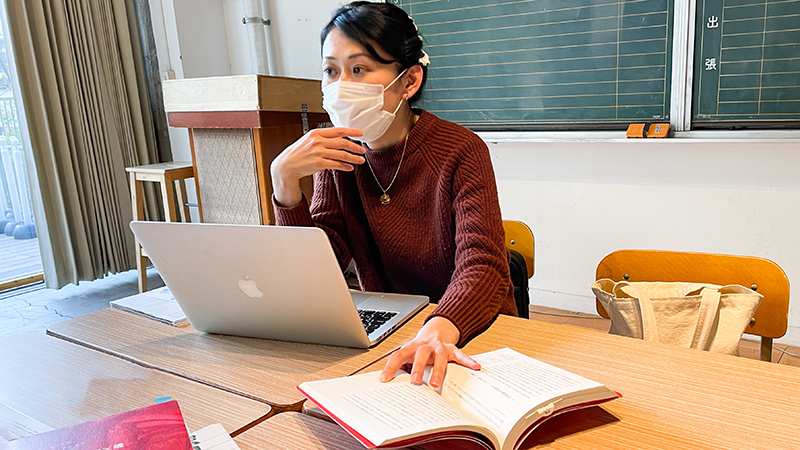
「アール・ブリュット」という言葉ひとつに、その国や地域の政治経済、地域性、社会課題、考え方、価値観が垣間見える、というお話には、非常にハッとさせられました。
20年にわたり、ヨーロッパで活動されてきた嘉納さんならではの視点であり、アートが世界中の人びとの暮らしと文化、歴史に密接にかかわっていることを再認識します。
後編では、アーツ千代田 3331でのポコラート事業や、これまでの展覧会、そして今後の活動についてお話をお聞きしていきます。次回もどうぞご期待ください。