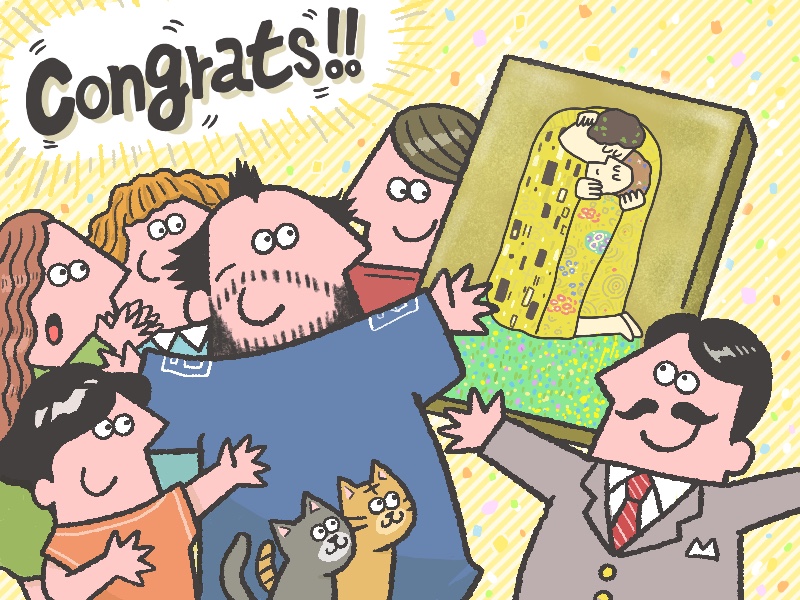
グスタフ・クリムト/10分でわかるアート
2022年6月15日

ナガサキピースミュージアム「切支丹、その出会い」展示風景
強制収容所やキリシタン迫害といった“人間の負”とも言える歴史から、「思考」を視覚表現し、現代に伝えるアーティストがいます。
彼女の名前は叶野千晶。東京を中心に、地方や海外でもフィールドワークを行い、視覚表現を用いた作品を発表しています。
本記事では、叶野さんのこと、作品やこれまでの展示のこと、そして8月に開催されるグループ展についてお聞きします。
──写真作品を多く発表されていますが、どのような技法やスタイルで撮影されていますか。
例えば、アウシュヴィッツ絶滅収容所を、人間によって変貌した「社会的風景」(70年代初頭のニュー・トポグラフィクス)としてハッセルブラッドカメラで撮影し、暗室でバライタ紙にプリントしました。
こちらは、GSSフォトアワード(ゼラチンシルバーセッション)で、最優秀賞を頂き、FUJIFILM SQUAREで展示。多くの方にご覧いただくことができました。

「GSS Photo Award 受賞写真『ラーゲルの記憶』」展示風景
また、大学での卒業制作では、太平洋戦争末期に武器を格納していた東京の残壕をゼラチンシルバープリントで制作したこともあります。
現在は、デジタルで撮影している作品が多いですが、場所や空間を利用した作品展示を考え、歴史や文脈を構成しながらコンセプト展示を行っています。

©Chiaki Kano ”Hidden Christian Story”
──これまでの作品を見ると、「戦争」「歴史」「宗教」などからインスピレーションを受けることが多いのでしょうか。そうなったきっかけがありましたら教えてください。
17歳の時に外からの環境の影響で身体と精神が疾患を抱えてしまい、部屋から出られなかったことがきっかけかもしれません。
この時に「アンネの日記」に出会い、ヨーロッパで起こった迫害(ホロコースト)の出来事を知りました。
オランダにあるアンネの隠れ家にも行ったことがありますが、狭く閉鎖的な部屋で生きる希望を捨てなかった彼女のことが強く印象に残り、心の支えになりました。
ホロコーストについて関心を持ったのは、チェコのプラハを訪れた時でした。ユダヤ人居住区、ゲットーに密集していたユダヤ人墓地を歩いていた時、まだ生き続けているような強いエネルギーを感じ、より深く関心を持つようになりました。
そこから「ホロコースト」がなぜ行われたのかと考えるようになり、さまざまな文献を読む中で、現代の社会問題にも結び付く出来事なのではないかと思うようになりました。
その後は、世界遺産にも登録されているチェコのトシェビーチ、ポーランドのアウシュヴィッツ、べウジェッツ、マイダネク、ドイツのダッハウなどの収容所でフィールドワークをしました。
──叶野さん自身、信仰する宗教はありますか。
特定の信仰する宗教はありませんが、母親の見えないものが見える、感じるといったスピリチュアルな体験を幼い頃から聞かされていました。
一緒に生活していた時は、毎朝、仏様が掘られた小さな彫刻に般若心経を唱えることで、「悪い霊がつかないように自分自身を守っている」と話していたことがあります。
教会や神社仏閣といった場所に意識が向くのは、こうした経験からかもしれません。

©Chiaki Kano ”Hidden Christian Story”
私は霊的なものを感じる力はありませんし、それを作品として見せるということに意識を向けていません。それよりも、自然や土地に対してのエレメントを感じ、それを作品に反映することに意識を向けています。
叶野さんは、2025年5月に長崎市の遠藤周作文学館にて、叶野千晶 写真作品展『サンタ・マリアの御像はどこ―遠藤周作の旅と情景を巡って―』を開催しました。
本展では、遠藤周作のエッセイ集『切支丹の里』をもとに、小説に登場する島原半島など各所を巡り写真で表現した作品を、遠藤文学の言葉とともに「思考と視覚の旅」をテーマに展示しました。

遠藤周作文学館(長崎市と文学館の協賛)で開催の一部
──叶野さんが初めに長崎を訪れたきっかけを教えてください。
長崎には過去に訪れたことがありましたが、コロナ禍の際に日本の島に行ってみたいと思い、以前から関心があった五島列島を縦断しました。
世界遺産に登録された後だったので、関連遺産として紹介されている福江島、奈留島、久賀島の教会や当時のかくれキリシタンが潜伏していた新上五島のキリシタン洞窟などを訪れました。
島に住んでいる人が話す歴史などを聞いた際に、長崎での宗教と自然との関わり方について関心が湧いたのがきっかけです。
──住み込みで取材したとのことですが、具体的にどのような方法で旧キリシタンについて取材しましたか?
住み込み取材は、2021年に外海地区で、下黒崎に住む7代目の旧キリシタン末裔の帳方、村上茂則氏の自宅を取材したことがきっかけでした。
お仏壇の前でオラショ(お祈り)を唱えていただいた際、「各地域によって信仰の仕方が違う」という話を伺い、実際に自分で確かめてみたいと思いました。

遠藤周作文学館(長崎市と文学館の協賛)で開催の一部
住み込みの時には生月島を訪れ、壱部集落で今でも信仰を続けている組の40分近くに渡る「唄オラショ」を聴きに行きました。
その際にご縁があり、後日解散した元触という組のご案内で、信仰の対象である安満岳に登ったり、平戸や生月島のかくれキリシタンの歴史が分かる場所を訪れました。
奈留島では、事前にアポイントを取っていた末裔の方に、現在開拓しているキリシタンが歩いていたという古道やお墓を案内してもらいました。
現地で当事者の方に案内をしてもらうことで、文献だけでは知り得ない歴史を体感することが出来るのではないかと思っていたので、文献に書かれていることと、現地での情報を参考にしながら、フィールドワークをしました。
──旧キリシタンの歴史や文化は、どのように作品に反映されているのでしょうか。
日本人伝道士が潜伏していたと伝わるバスチャン屋敷、日本で最初のキリシタン大名と言われている大村純忠の最後の住処跡など、ランドスケープを中心に撮影をしました。
また、お掛け絵や踏み絵など旧キリシタンが神として大切に崇めていた信仰具も撮影しました。
生月島のお堂で撮影させていただいたお掛け絵は絹に描かれたもので、聖マリアの姿は美しいと感じました。

©Chiaki Kano ”Hidden Christian Story”
西洋風の図像だったので気になり調べたところ、イエズス会が定めたキリシタンを象徴する「十五玄義図」(ロザリオの聖母)の一部であることが分かりました。その後、元の図像が見つかった大阪・下音羽地区の取材にも行きました。
旧キリシタンは、次に受け継ぐ世代がいなくなり消滅をしてしまう伝統であります。
しかし、今日まで信仰が続いてきたこと、守られてきたことの精神的な繋がりや歴史を含めて、現代に住む当事者の方の思いを受け止めて、作品として伝えたかったことがあります。
──遠藤周作の文学と自身の作品を結びつけることで、新たに見えてくる社会的な問いや問題はありますか。
遠藤周作は少年の時に、基督教の洗礼を受けた(受けさせられた)ことで、信仰に対する生き方を問い続け、長崎でそれを見つけました。
エッセイ「人生の踏絵」の中でも、「『神の沈黙』ー沈黙のまま歴史の中へ葬り去られた人間たちに声を与えたい」と書かれてありますが、この言葉は共感が出来るものがあります。

©Chiaki Kano ”Hidden Christian Story”
遠藤は、一枚の踏絵と出会ったことで、与えられた使命を小説家として果たそうとしたのだと思います。
その踏絵は、黒い足指の痕がついた聖マリアの踏絵です。遠藤は、この沢山の人が踏んだ痕跡から、踏絵を踏んだ人と踏まなかった人、弱者と強者について思いを馳せました。
人それぞれ信仰の強さや思いがあると理解しつつ、弱者の立場に向き合い、寄り添おうと考えていたのかもしれません。
長崎での展示では、遠藤文学の代表作「沈黙」の冒頭に出てくる雲仙地獄で夜に撮影した湯けむりを49点組み合わせ、イメージを再構築した作品を展示しました。
拷問に連れて行かれるまでの情景を書く中で「自分たちは信奉する教えを絶対に捨てぬ」という信者の芯の強さを、遠藤の言葉と照らし合わせました。
──目に見えない、失われていく歴史、風景、人の想いは写真をはじめとする「視覚芸術」で残せると思いますか。
私たちが生きている現代は、非常に速いスピードで時が流れています。
昨日あった出来事さえ過去のものとして、忘れ去られていくように感じます。写真はその記憶を想起させる力があると信じたいですし、想像すること、考えさせられる主題に向き合うことを続けてきました。
人それぞれの関心や経験によるものではありますが、現代の問題提起を更新すること発信すること、それはドキュメンタリーとアートととの関係を探求することにつながることだと考えています。
──「壁景」という作品を展示されるとのこと、こちらはアウシュヴィッツ絶滅収容所を実際に取材し制作されたものなのでしょうか。
ポーランドには、6つの絶滅収容所施設と呼ばれている場所が存在します。アウシュヴィッツ絶滅収容所が最大の霊園であり、ここには2回訪れました。
今回出展する「壁景」の場所は、ルブリン市のマイダネク収容所で撮影した作品です。
壁のテクスチャーを再現するために、中世ルネサンス時代のフレスコ画の漆喰がベースである印画紙で制作しました。

2021年に開催した「WALL-SCAP」展示風景
この収容所は当時のままの状態で保存されているもので、見た目は家畜用の小屋を改装して、シャワー室に見立てています。
奥に入るにつれて暗くなる空間よく見ると、壁にシアン化で変色した青いシミがあることが目につきました。
それがまるで抽象画のように見えましたが、読んでいた文献からここがガス室であったことが分かりました。ここで、撮影をしていると、まるで死者の声が聞こえてくるようなザワザワした感覚を覚え、怖くなることもありました。
さらに奥には独房もあるのですが、外から入る自然光に、ここで起こった出来事がまるで“錯覚”であるかのような不思議な感覚になります。
マイダネク収容所は、巨大な死体焼却炉の灰も当時のままの状態としてモニュメントという形式で残されていて、私たちが生きている現代とのギャップを考えさせられる場所でありました。
──戦後80年。この作品をこのタイミングで展示する理由をお聞かせください。
企画のコンセプトが、戦後80年の終戦を起点にした作品の「風化=”戦争と無意識の間”」です。その際に、「壁景」の作品の展示の話がありました。

2021年に開催した「WALL-SCAP」展示風景
「記憶が残されている場所」は、日常の生活や時間に追われるなかで本当の豊かさとは何かを教えてくれるように感じます。
日本に住んでいると平和が当たり前のように感じます。戦争は現代でも起きているので、そのことについて考えることが大切なのではないでしょうか。
私は過去の記憶を忘れないために、作品を制作しているのかもしれません。
社会の中で戦争を経験していない世代が、どのようにして考える機会が得られるか、どんな歴史を経て、私たちはこの世紀に生きているのかということを、芸術という領域を通して考えるきっかけになればと切に願っています。
叶野さんの作品が見られるグループ展は8月16日(土)から。神楽坂の√K Contemporaryで鑑賞可能です。