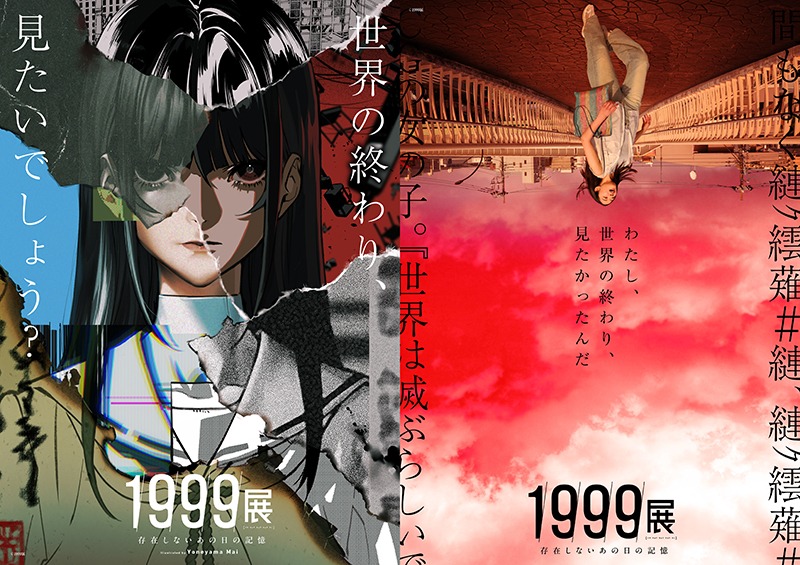
テーマは『世界の終わり』。ホラー体験が楽しめる展覧会が7月開催!【六本木ミュージアム】
2025年6月19日
今回の「10分でわかるアート」では、私たちにとって身近な神様でさまざまな幸福をもたらす七福神を紹介します。
七福神は日本で信仰されている神様で、恵比寿、布袋、毘沙門天、大黒天、弁財天、福禄寿、寿老人の七柱で構成されています。
元々は人や仙人、インドや中国からやってきたとされる神様がいるなど個性豊かな経歴を持つ七福神。確立したのは、江戸時代中期ごろと言われています。

歌川豊国(3世)《七福神宝船》弘化4-嘉永5 東京都立中央図書館蔵 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000003-00049168(2024年8月26日閲覧)
ここからは、それぞれがどんな神様かを紹介します。

釣り竿と鯛を持っている神様。漁業、農業、商業の神様として商売繁盛や大漁・豊作のご利益があります。
恵比寿は七福神の中で唯一、神道あるいは日本神話の神を起源としており、その起源は日本神話におけるイザナギとイザナミの最初の子とされています。

実在した人間が神格化されたという神様。中国の唐代末期から五代十国時代にかけて活動したとされる仏僧で、ふくよかなお腹と大きな袋を担いでいるのが特徴です。
夫婦円満と人徳の神様で、金運や出世運なども含めさまざまな運が向上すると言われています。
布袋は不思議な力をもっており、人の吉凶を見事に言い当てたといった逸話も残っています。

鎧を着て武装している姿の神様。戦いの神として知られています。
勝運や厄除けのご利益があり、単独で祀られる場合には「多聞天」とも呼ばれます。
インド出身の神様で財宝神「クヴェーラ」が仏教に取り込まれて誕生しました。
福の神であるとともに、インドから日本に伝播する過程で軍神・武神としての性格を得た異色の神様でもあります。

米俵の上で打ち出の小槌と大きな袋をもっている神様。
大黒天が持っている袋の中身は宝物であり打ち出の小槌が富の象徴であることから金運や開運、縁結びのご利益、勝負運などのご利益があります。
大黒天もインド出身の神様で、ヒンドゥー教の破壊神シヴァの異名です。仏教に取り入れられて大黒天となりました。

七福神の中で唯一の女性の神様で、琵琶を弾いている姿が特徴です。
「弁天さま」の愛称で親しまれ、芸能の神様として音楽や芸事の才能を開花させるご利益があります。
弁財天もインド出身の神様で、河と学芸の女神サラスバティーが仏教に取り込まれて誕生しました。
弁財天を祀る仏閣としては日本三大弁天である宝厳寺、大願寺、江島神社が代表的です。

鶴を従えた仙人のような姿の神様。子孫繁栄や財運招福、延命長寿などのご利益があります。
古代中国の道教に起源をもつ神で寿老人と同一視されることもあります。
古代中国では天体を神格化した星辰崇拝(せいしんすうはい)という信仰があり、福禄寿は南極老人星(カノープス)を神格化した存在です。
仏教においては弥勒菩薩の化身とされています。

調和を象徴する鹿を従え、「不死の霊薬」が入ったひょうたんと不老長寿のシンボルである桃を持っている神様。
福禄寿とは同体異名の神とされていますが、ご利益においては長寿のみに特化しています。

河鍋暁斎《布袋の図》 東京都立中央図書館蔵 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000003-00221546(2024年8月26日閲覧)
布袋は禅僧の水墨画の画題におおく取り上げられていたこともあり、水墨画を中心としての数多くの作品に描かれています。
河鍋暁斎(かわなべきょうさい) の《布袋の図》は、布袋が「見ざる・聞かざる・言わざる」のポーズを取った子どもたちを担いで川を渡るようすを描いたユーモアな作品です。
また、七福神といえば宝船に乗っているイメージが強いのではないでしょうか。
静静嘉堂文庫美術館(東京・丸の内)には、岩﨑小彌太(いわさきこやた)の還暦を祝し、孝子夫人が京都の人形司・丸平大木人形店に依頼した御所人形が所蔵されています。
運が良ければ、雛祭りの時期に開催される企画展で、観ることができるかもしれません。

歌川芳虎《新板福神双六》 東京都立中央図書館蔵 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000004-00000301(2024年8月26日閲覧)
歌川芳虎は幕末から明治初期にかけて活躍した浮世絵師です。
七福神をモチーフにした浮世絵も複数制作しており、《新板福神双六》もその一つ。
双六という遊び道具の挿絵にも採用されるとは、七福神が江戸時代の一般大衆にも広く親しまれていたことがわかりますね。

歌川国貞《七福神恵方入船》東京都立図書館蔵 https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/detail?tilcod=0000000003-00052436(2025年1月16日閲覧)
《七福神恵方入船》は歌舞伎・浄瑠璃の外題(*)を題材とした歌川国貞の作品です。
*外題(げだい):芝居・講談などの題名のこと。
宝船に乗っている七福神を、当時人気だった歌舞伎役者に見立てて描いています。
七福神を調べてみると、日本の神様ではなく、インドや中国発祥の神様もまざっているのは意外でした。
七福神をモチーフにした作品はジャンル問わず幅広く、今も昔も幸福を願う人びとの拠り所となっています。
七福神にゆかりのある神社をめぐってみたり、七福神の美術作品に触れてみると何かいいことが起こるかもしれませんね。
10分でわかるアートとは?
「10分でわかるアート」は、世界中の有名な美術家たちや、美術用語などを分かりやすく紹介する連載コラムです。
作家たちのクスっと笑えてしまうエピソードや、なるほど!と、思わず人に話したくなってしまうちょっとした知識など。さまざまな切り口で、有名な作家について分かりやすく簡単に知ってもらうことを目的としています。
「この作品を作った作家についてもう少し知りたい!」「美術用語が難しくてわからない・・・」そんな方のヒントになれば幸いです。
【参考書籍】
山折哲雄監修『キャラ絵で学ぶ!神道図鑑』 (株)すばる舎 2020年