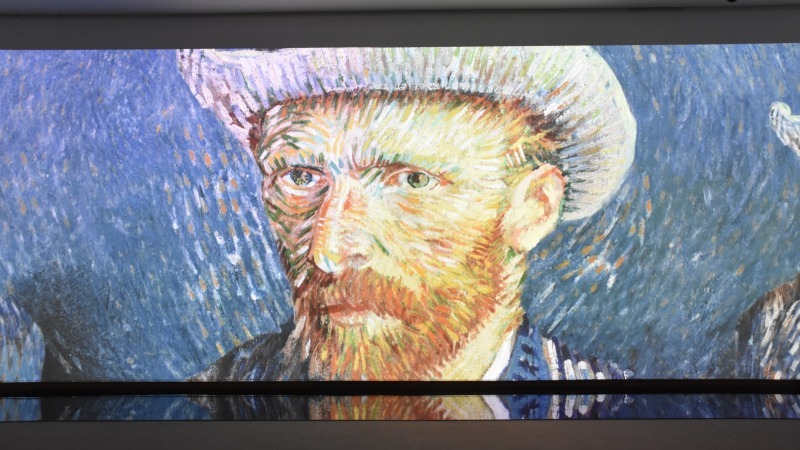
国内初展示や限定グッズも!ファン・ゴッホの夢を繋いだ「家族」の物語【愛知県美術館】
2026年1月21日
ミケル・バルセロ展/東京オペラシティ アートギャラリー
現代スペインの代表的アーティスト、ミケル・バルセロ(1957-)の日本初となる回顧展が、東京オペラシティ アートギャラリーにて開催中です。

国立国際美術館、長崎県美術館、三重県立美術館と巡回してきた本展は、ついに最終会場である東京オペラシティ アートギャラリーに。彼の仕事の全貌を紹介する展覧会となっています。
※展覧会情報はこちら
ミケル・バルセロは、1957年にスペインのマジョルカ島で生まれました。1982年に開催された国際美術展「ドクメンタ7」で画家としてデビューして以来、マジョルカ島をはじめ、パリ、アフリカのマリ、ヒマラヤなど世界各地で制作を続けています。
その制作は、絵画だけでなく、彫刻や陶芸、パフォーマンスなど多岐に渡ります。近年ではマジョルカ島のパルマ大聖堂の内部装飾や、スイスのジュネーブにある国連欧州本部人権理事会大会議場の天井画などの壮大な建築プロジェクトを手がけるなど、アーティストとしてのキャリアを着実に重ねています。2013年にはフランス文化省より芸術文化勲章「オフィシエ」を、2020年にはスペイン・カタルーニャ自治州政府よりサン・ジョルディ十字勲章を受章しました。

ミケル・バルセロ、マジョルカ島ファルーチのアトリエにて、2020年
撮影:ジャン=マリー・デル・モラル
Photograph by Jean-Marie del Moral
www.jeanmariedelmoral.com
バルセロは、日本においてはいわば「幻の作家」といえるでしょう。欧州では広く知られ尊敬を集める存在ですが、日本では1990年までのわずかな例外をのぞき、まとまった作品の展示が久しく行われていないのです。これだけ現代アートにおいて重要な作家であるにも関わらず、なぜ、今まで日本で紹介されてこなかったのでしょうか。
本展を担当した福士学芸員に伺ったところ、複合的な要因が絡まっていて一言で伝えるのは難しいようですが、主に以下5つの理由が考えられるそうです。
では、今回なぜ開催に至ったのでしょうか。その理由について福士学芸員は次のように語ります。
「表面的な『最先端』からは微妙に外れていても、充実した活動、より今日的なアクチュアリティのある活動を行っている作家はたくさんおり、そうした作家の仕事を日本のオーディエンスにもっと伝えたいという関係者の熱意がまずあったかと思います。バルセロは類のないエネルギーで充実した活動を続けており、その作品を評価する美術館関係者の力を結集して今回の展覧会の実現にこぎつけました。」

「ミケル・バルセロ展」展示風景
展覧会の開催において、輸送コストの問題は大きいもの。90点もの作品が日本に一堂に会する機会はそうそうないと思われるため、本展は非常に貴重な展覧会でもあります。
バルセロは1980年代の新表現主義の流れを汲む画家と言われています。
新表現主義とは、1970年代後半から1980年代中ごろにアート界を席巻したひとつの動向のこと。1970年代に流行していたコンセプチュアル・アートやミニマル・アートの難解さ、禁欲的な表現に対抗するように生まれました。
代表的な作家は、アンゼルム・キーファー、ジャン=ミシェル・バスキアなど。荒々しい筆致と原色を多用した色彩が特徴的です。
バルセロの野性味あふれる作風も、当初は新表現主義の典型として受け取られましたが、彼の表現媒体は、絵画だけではなく彫刻や陶芸など多岐に渡ります。
そのテーマの大きな位置を占めるのは、海と大地、動植物、歴史、宗教など。最近作である《下は熱い》(2019)に地球環境問題を、《たくさんの蛸》(2020)に難民危機を見て取る人もいる、と福士学芸員は言います。

《下は熱い》(2019)

《たくさんの蛸》(2020)
また、一見自由奔放に描いているように見えますが、実は美術的な文脈を押さえている画家でもあります。
例えば、バルセロは闘牛のモチーフを多く描いていますが、これはゴヤやマネ、ピカソなど過去の偉大な画家たちも主題として扱っていました。

《銛の刺さった雄牛》(2016)
また《銛の刺さった雄牛》(2016)では、グラインダーでキャンバスを切りつける表現を用いています。これには、カンヴァスに切り込みを入れた「空間概念」シリーズで著名なイタリア人画家、ルーチョ・フォンタナの影響を見て取ることもできます。

《銛の刺さった雄牛》(部分)
2020年に制作された《漂流物》(2020)には、ヴェルレーヌ、ポーやイェーツなど、バルセロが愛読してきた詩人の名前が描かれています。こういった細部からもバルセロの広い知識や教養が伺えます。

《漂流物》(2020)
こうした文学や美術史についてのバルセロの教養は、母親の存在が強く影響しているそうです。

《母》(2011)
母親の書棚にあった300人におよぶ画家たちの画集や伝記などを読みふけって育ったバルセロ。今でも母親とマスコミの前に登場することもあるのだとか。
バルセロの絵に頻繁に登場するモチーフが、“闘牛”です。

《とどめの一突き》(1990)
孤独な闘牛士と、絵画を制作する自分とをなぞらえているようです。

《イン・メディア・レス》(2019)
最近では、海洋生物やメロンがお気に入りのモチーフだそうです。

「ミケル・バルセロ展」展示風景

《開いたメロン》(2019)
生や死に関するモチーフも多く登場します。

《雉のいるテーブル》(1991)
本作にも海洋生物であるエビが描かれています。
最後に、バルセロが多く描いた肖像画を紹介します。これはブリーチペインティングと呼ばれる手法で描かれており、暗色に塗った上から漂白剤で脱色して描いているそうです。

「ミケル・バルセロ展」展示風景
ブリーチペインティングは、時間が経つと描いたものが浮き上がってくる仕組みになっているので、描いてる時はどのように完成するのか確認できません。コミュニケーションを取るときの、こわごわと相手を知っていくようすと手法が合っているように感じました。
また、絵画の他にも彫刻や陶芸作品などが展示されています。

《マッチ棒》(2005)

《カピロテを被る雄山羊》(2006)
メロンや蛸など、ひとつひとつのモチーフの意味を想像しながら楽しむこともできそうです。
また、本展は近作から過去作に遡るように展示されています。奥に進むにつれて作家個人の内面にクローズアップしていくような構成だと感じました。

《ファラニチのジョルジョーネ》(1984)
当初、写真で作品を見た時は、その色彩とモチーフから自由奔放な印象を受けていました。しかし、実際に観てみると、迫力はもちろんのこと、美術だけでなく音楽や文学の知識に裏打ちされた画家でもあるのだと感じました。

《細長い図書室》(1984.02-1985.03)
バルセロの作品を国内で約90点も観ることができる機会はめったにないので、この機会にぜひ足を運んでみてください。
なお、作品の撮影は、可能なものと不可のものがあります。撮影の際には、館内の指示に従ってください。
作品すべて©ADAGP, PARIS & JASPAR, TOKYO, 2021.